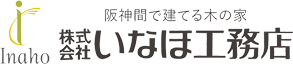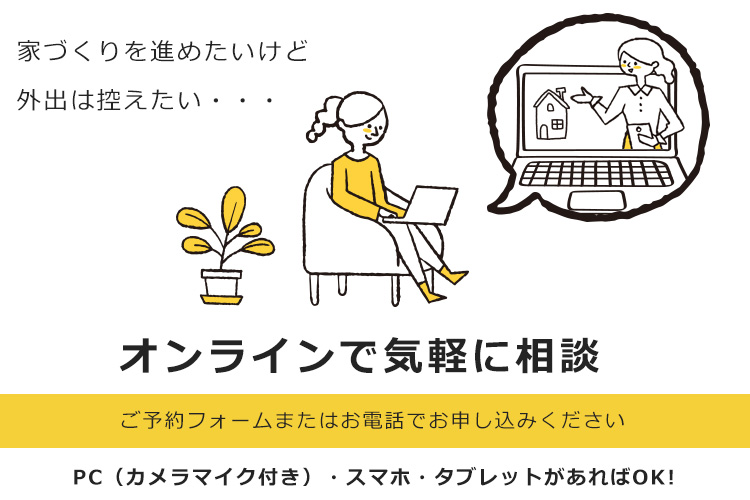ご存じですか?内装制限
2022/10/24 | お家のこと TOPICSこんにちは、薪ストーブも大好きないなほ工務店です。
建築物を建てる時、多数の制限が設けられているのはご存じの方も多くいらっしゃるかと思います。
有名なところで上げさせていただくと、建ぺい率や高さ制限などもその1つです。
今回のコラムでは、そんな制限の中から建物の内部にかかる制限。
内装制限についてお伝えいたします。
そもそも内装制限とは?
内装制限とは、建築基準法に定められている規制の1つで、壁や天井の仕上げに燃えにくい材料を使用することで、火災が起きた場合、火の燃え広がりや煙(有毒ガス)の発生を遅らせることを目的としています。
炎が急拡大した場合でも、避難できるよう室内の仕上げに準不燃材料または、難燃材料の使用が義務付けられているのです。
壁や天井というと、床は?と思われるかもしれませんが、床は制限の対象外です。
理由は、炎や煙は上に向かう性質があるためです。
ちなみに、防火区画に限り建具にも制限がありますが、通常の住宅の場合気にする必要はありません。
多種多様の建築物に設定されている内装制限
内装制限の対象となる建築物は、多種多様で、劇場や映画館、病院やホテル。
下宿や共同住宅の他、飲食店や百貨店など、建物の用途によって定めが違います。
| 用途① | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 |
|---|---|
| 用途② | 病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、ホテル、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む) |
| 用途③ | 飲食店、物品販売業を営む店舗、百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店 |
| 用途④ | 自動車車庫、自動車修理工場 |
| 用途⑤ | 地階にある上記①~③の用途部分 |
| 用途⑥ | 大規模建築物 |
| 用途⑦ | 住宅のキッチン |
| 用途⑧ | 住宅以外の調理室、ボイラー室など |
| 用途⑨ | 内装制限における無窓居室 |
| 用途⑩ | 温湿度調整を要する居室など(法28条1項ただし書き) |
①~⑤の用途は広さや客席数によっても更に細かく区分されていますが、こちらのコラムでは住宅に関する区分の、住宅の「火気使用室」に当たる⑦と⑩についてご紹介させていただきます。
火気使用室という考え方
「火気使用室」耳慣れない言葉で分かりにくいかもしれませんが、住宅内で火を直接使用する設備が固定されている場所が、それにあたります。
上記区分の、⑦住宅のキッチンはコンロにて直接火を使う場所という意味で分かりやすいですが、用途⑩の温湿度調整を要する居室が火を使う場所として「火気使用室」の定義をされている理由は少し分かりにくいですよね。
温湿度調整を要する居室なんてすべての部屋じゃないの?と思わるかと思いますが、この場合「温湿度調節」に使用する設備が重要になります。
居室の「温湿度調節」を行う設備が、直接火を使う固定式のストーブ(代表例は薪ストーブ)や壁付けの暖炉が設置されている部屋のことを指しているからです。
上記の他にも、浴室も対象に含まれますが、戸建て住宅の場合、キッチンなど火を扱う部屋が「平屋の建物にある場合」や「2階建ての2階部分など建物の最上階にある場合」には内装制限の対象にはなりません。
ちなみに、IHコンロも直接火を使わないので、内装制限は免除されます。(市町村によっても違うので、阪神間で家を建てたいなと思われる方は、お尋ねください。)
そのため、キッチンにも木をふんだんに使用し、木を見せるデザインにしたい場合は、IHコンロを採用される方もいらっしゃいますよ。
内装制限の緩和について
火事の恐れを軽減するため制限が設けられている内装材ですが、2009年4月に緩和されました。
従来の建築基準法施行令による規定では、オープンキッチンの場合、垂れ壁を設けない限り、LDK全体が内装制限の対象となっており、内装材の選択に制限がありました。
この制限が改正によって、キッチンのコンロ周り(コンロ中心から半径250mm、高さ800mm)を特定不燃材で仕上げることで、他の部分は適用対象外にすることが可能です。

キッチン上に設置してある白い円形状のものがそれにあたります。
特定不燃材料一覧
- コンクリート
- レンガ
- 瓦
- 陶磁器質タイル
- 繊維強化セメント板
- 厚さが三ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板
- 厚さが五ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
- 鉄鋼
- 金属板
- モルタル
- 漆喰
- 石
- 厚さが12㎜以上の石膏ボード(ボード用原紙の厚さが0.6㎜以下のものに限る。)
- ロックウール
- グラスウール板
薪ストーブを設置したい場合はどうなるの?
上記でご説明した通り、薪ストーブも内装制限の対象です。
つまり・・・薪ストーブを置く場所も不燃材で覆わなければいけないことになります。
薪ストーブを置く場所は、基本的にリビングかダイニング。
人が集まる場所ですよね。

人が集まる場所はより快適に、より素敵に仕上げたいのは当然なので・・・こちらも上記でご案内した、内装制限の緩和
・可燃物燃焼部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げにあっては、特定不燃材料ですること
・上記に掲げる部分以外の部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げにあっては、木又は難燃材料等ですること
を、利用します。
しっかり計算することで、薪ストーブから5方向の燃焼距離の範囲に特定不燃材量を使うだけで済みます。
その他は、木や難燃材料等が使用できるので、理想の空間を作ることが可能です。

まとめ
建築物を建てる際には、様々な法律が関わってきます。
公共施設なら多くの人が長きに渡り安全に使用できるものである必要があり、住宅ならそこで暮らす人が安全で安心して過ごせるように建てる必要があるのですから当然と言えば当然です。
でも、法律に合わせていればどんな家でも良いというのもまた違うと思います。
大切なことは、法律に即しながらも好きなデザインで住み心地の良い安全な家であるという事ではないでしょうか。
住宅の法律だけでも多くの規制や規則があり、ややこしい内容ばかりですが、簡単にでも知識として事前に知っておくことで、好きな空間を考える際にも、イメージしやすくなりというメリットがあります。
分かりにくいな・・・。
私たちが家を建てる予定の土地にはどんな規制があるのかな?等、気になることがございましたらお気軽にご質問くださいね。